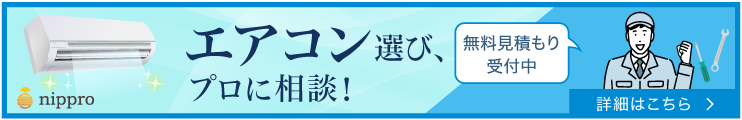エアコンの「水」の正体とは?ドレン排水はどうやってできるの?
2025.07.28 UPDATE

エアコンを運転していると、室外機のそばから水がポタポタと落ちているのを目にすることがあります。これは「故障かな?」と心配になる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。
この水の正体は「ドレン水」といい、実はエアコンが室内の空気を快適に保つために欠かせない、正常な現象なのです。
では、一体なぜエアコンは「水」を作り出すのでしょうか?そして、その水はどこから来て、どのように屋外へと排出されるのでしょうか?
この記事では、エアコンのドレン排水がどのようにできて、どこへ排出されるのか、順を追って解説します。ドレン排水の仕組みを理解していきましょう^^
エアコンのドレン水とは?
エアコンが水を生み出す原理は「結露」が鍵
エアコンの冷房は、単に空気を冷やすだけでなく、同時に空気中の湿気(水蒸気)を取り除くことで、より体感温度を下げ、快適さを向上させる機能を持っています。この湿気を取り除くプロセスが「除湿」であり、その際に水蒸気が水滴となって排出されるのがドレン排水です。
「結露」の仕組みは身近にも

私たちは日常生活で様々な場面で結露を目にします。たとえば、夏の暑い日に冷たい飲み物を入れたグラスの表面に水滴が付いたり、冬の寒い朝に窓ガラスに水滴が付いたりするのも、すべて結露です。
では、なぜ結露が起こるのでしょうか? 空気中には、目に見えない「水蒸気」が含まれています。この水蒸気は、空気の温度が高いほどたくさん含むことができますが、温度が下がるとその「水蒸気を含むことのできる限界量(飽和水蒸気量)」が低下します。すると、空気中に含みきれなくなった水蒸気が、小さな水滴へと姿を変えるのです。これが結露の基本的な発生原理です。
エアコンの内部でもこの結露の原理がはたらいて、効率的に室内の空気中に含まれる水分が取り除かれていきます。
エアコンの主な運転モードは以下の通りで、それぞれ水の排出の有無が異なります。
冷房運転
室温を下げる際、同時に除湿も行います。そのため、大量のドレン排水が発生します。
除湿運転(ドライ運転)
室温をあまり下げずに湿度を下げるモードです。冷房運転よりも緩やかに冷却するため、冷房ほどではないにしても、やはり結露が発生し、ドレン排水が生じます。
暖房運転
空気を温めるため、結露は発生しません。そのため、ドレン排水も基本的に排出されません。ただし、霜取り運転中は室外機で結露水が発生し、それが排出されることがあります。
エアコンのドレン水は、どうやってできるの?
エアコンの室内機内部では、この結露現象を効率的に利用し、室内の空気から水分を取り除いています。ドレン水は次のような仕組みで発生します。
エアコンのドレン水ができるまで
ステップ1:熱交換器(冷却コイル)で空気を冷却
エアコンが冷房運転を始めると、まず室内の暖かい空気を吸い込みます。この吸い込まれた空気は、室内機内部の重要な部品である「熱交換器」を通過します。
熱交換器は、内部に**冷たい冷媒(フロンガスなど)**が循環する管が網の目のように配置されており、その周りには多くの薄い金属製のフィン(ひだ状の板)が付いています。冷房運転中、この熱交換器はキンキンに冷やされており、まさにエアコンが冷気を作り出すための中心的な役割を担っています。
ステップ2:水蒸気が水滴へと変化する「結露」の瞬間
暖かい空気が、この冷たい熱交換器の表面に触れると、空気の温度は急激に低下します。
このとき、暖かい空気に大量に含まれていた水蒸気は、温度が急に下がったことで飽和水蒸気量が減り、含みきれなくなった余分な水蒸気が熱交換器の冷たい表面に水滴となって付着し始めます。これが、エアコン内部で発生する結露です。
エアコンの冷房運転には「除湿効果」がありますが、まさにこの結露の原理によって、空気中の余分な水分が取り除かれています。お部屋を涼しくすると同時に、ジメジメとした湿気も解消してくれるのは、この働きがあるからなのです。
ステップ3:ドレンパンで結露水を集める
熱交換器の表面に付着した水滴は、重力によって下へと流れ落ちていきます。これらの水滴を効率的に集めるために、熱交換器の下には「ドレンパン」と呼ばれる受け皿が設置されています。
ドレンパンは、熱交換器全体から滴り落ちる結露水をしっかりと受け止め、一箇所に集める重要な役割を担っています。これにより、発生した水がエアコン内部の電子部品にかかったり、お部屋の中に漏れ出したりするのを防いでいます。
発生したドレン水は「ドレンホース」から室外へ排出
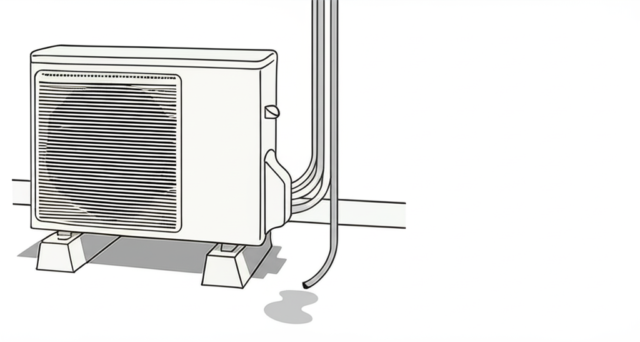
ドレンパンに集められた結露水(ドレン水)は、安全に屋外へ排出する必要があります。そう、室外の「ドレンホース」から出てくる水の正体は、結露水だったのです。
自然の勾配を利用した排水方法
ドレンパンに集められた水は、そこからドレンホースという細い管を通って、室外へと排出されます。皆さんがエアコンの室外機のそばで水がポタポタと落ちているのを目にするのは、このドレンホースの先端から出てきた水なんですね。
ドレンホースは、ドレンパンよりも低い位置に設置され、水の重力(自然な勾配)を利用してスムーズに排出されるように設計されています。特別なポンプなどを使わずに、自然の力だけで水を排出する、非常にシンプルで効率的な構造です。
ドレン排水の量はなぜ変動するの?
エアコンから排出されるドレン排水の量は、常に一定ではありません。その量は、いくつかの環境要因によって大きく変動します。
- 室内の湿度: 部屋の空気がジメジメしている(湿度が高い)ほど、空気中に含まれる水蒸気量が多くなるため、熱交換器で結露する水の量も増え、ドレン排水は多くなります。特に、日本の梅雨時や真夏日は、多量の水が排出されるのが一般的です。
- 室温と設定温度の差: 室内の温度とエアコンの設定温度の差が大きいほど、熱交換器で空気を冷やす度合いが大きくなり、結露量も増えます。例えば、非常に暑い日に設定温度を低くすると、より多くの水が排出される傾向にあります。
- エアコンの運転時間: エアコンの運転時間が長ければ長いほど、結露し続ける時間も長くなるため、ドレン排水の量も増えます。
- 部屋の気密性・断熱性: 部屋の気密性や断熱性が低いと、外の湿気が入り込みやすいため、ドレン排水の量が多くなることがあります。
このように、ドレン排水の量は、エアコンの除湿能力と、室内の環境に密接に関わっているのです。
ドレン水発生は快適空間を作るための正常な現象!

エアコンから水が排出されるドレン排水は、エアコンが正常に働き、私たちの生活空間を快適に保つ上で欠かせない現象です。
その過程には、空気中の水蒸気が冷たい熱交換器に触れて「結露」し、その水が集められたドレンパンから、最終的にドレンホースを通じて室外へ排出されています。
ドレン排水の一連の働きを理解することで、エアコンからの水は、単なる排水ではなく、「除湿」という大切な機能が働いている「証」であることがお分かりいただけたかと思います。
エアコンのことなら札幌ニップロに相談を
📞 電話で今すぐ相談したい方
🕘 【営業時間】9:00〜17:00/⛔ 日曜・祝日定休
✉️ フォームで気軽に問い合わせたい方
📞 LINEで手軽にチャット相談したい方
スマホからすぐに相談OK!写真を送って「うちでも設置できる?」といった質問も可能です。