【症状別】ロードヒーティングが動かない?主な原因と対処法のまとめ
2025.11.06 UPDATE
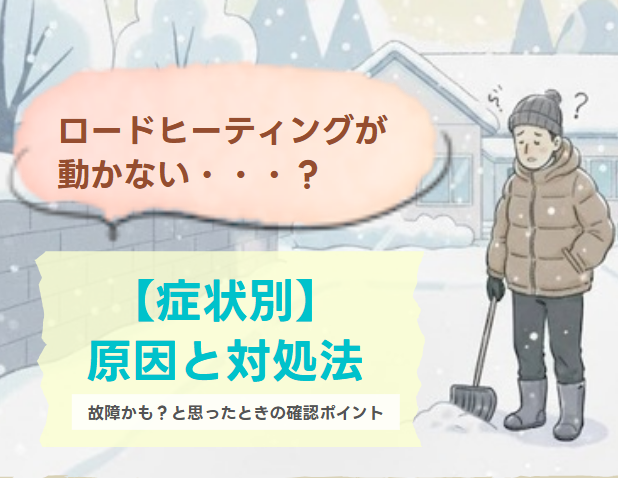
雪の季節になると頼りになるロードヒーティング。
でも朝になってスイッチを入れても「動かない」「雪が全然溶けない」となると焦りますよね。
もしかして故障かもしれないと感じる方も多いはず。
この記事では、ロードヒーティングのよくある故障症状と考えられる原因・対処法をわかりやすくまとめました。
動かなくなったとき、まず何を確認すべきかも紹介します。
あわてず落ち着いてチェックしていきましょう。
目次
故障かも?と思ったら、まずはこのチェックを
ロードヒーティングが動かないからといって、故障とは限りません。まずは基本的なポイントを確認してみましょう。
- 電源は入っていますか?
- ブレーカーは落ちていませんか?
- リモコンやコントローラーの設定は正しいですか?
- タイマー設定や温度設定は適切ですか?
意外と、このあたりの確認だけで不調が復旧するケースもあります。
それでも動かない場合は、具体的な症状から原因を探っていきましょう。
症状別に見る!ロードヒーティングの原因と対処法
ロードヒーティングの故障は、その症状によって原因が異なります。ここでは、よくある3つの症状に分けて、考えられる原因と対処法を解説します。
【症状①】まったく動かない・電源が入らない
電源がまったく入らないときは、システム全体に電気が届いていないか、内部の制御部分に不具合がある可能性があります。
考えられる原因
- ブレーカーの不具合
電力を多く使うロードヒーティングは、過負荷や漏電でブレーカーが落ちることがあります。頻繁に落ちる場合は、配線や機器本体の故障の可能性も。特に、同じブレーカー回路で他の電化製品を同時に使った場合や、漏電が発生した場合に起こります。
- 電源ケーブルや配線の断線
経年劣化や小動物(ネズミなど)による被害で切れてしまうケースも。屋外配線は特に注意が必要です。
- コントローラーやヒューズの故障
リモコン表示が消える、操作できないといった症状がある場合はこの可能性が高いです。電源を制御するコントローラー本体や、内部のヒューズが故障している可能性があります。
- センサーの故障
雪や気温を感知するセンサーが壊れていると、作動すべき状況を認識できずに止まってしまうことがあります。センサーが異常な数値を検知すると、安全装置が働いて停止することもあります。
センサーは消耗品であり、交換で対応できるケースが多いです。
自分でできる対処法
・分電盤の確認
分電盤のロードヒーティング用ブレーカーが「切」になっていないか確認。落ちていたら「入」に戻します。
ただし、すぐ落ちる場合は危険なので業者に依頼を。
・リモコンの再設定
一度電源を切って数分後に再起動してみましょう。設定がリセットされて動作が戻る場合もあります。
これらの対処法でも改善しない場合は、専門業者による点検・修理が必要になります。無理に自分で配線を触ったり分解したりすると、感電やさらなる故障の原因になるので絶対にやめましょう。
【症状②】温まらない・雪が溶けない
電源は入っているのに雪が溶けない。
そんなときは、熱を作る・運ぶ部分のトラブルが考えられます。部分的に雪が残る「ムラ」にも要注意です。
考えられる原因
- サーモスタットの故障
温度を一定に保つためのサーモスタットが故障していると、正常な加熱ができません。設定温度になっていないにもかかわらず作動を停止してしまうことがあります。
- ヒーター線の部分的な断線(電気式)
電気式のロードヒーティングの場合、地中に埋められたヒーター線の一部が切れてしまうと、帯状に雪が溶けないエリアができます。断線箇所の特定は専用機器が必要です。
- 温水ボイラー本体の不具合(温水式の場合)
点火不良、給排気口の詰まり、内部部品の経年劣化などにより、そもそも温水が作られていない可能性があります。
リモコンにエラーコードが表示されていないか確認してみましょう。特に設置から10年以上経過している場合、ボイラー本体の交換時期になっているケースも多いです。
- 不凍液の不足・エア抜き不足(温水式)
温水式のロードヒーティングは、ポンプで循環させる不凍液によって熱を運びます。
不凍液が不足していたり、システム内に空気が溜まると、不凍液の循環が妨げられて熱がうまく循環しません。不凍液は通常7~8年に一度の交換が理想です。
- 循環ポンプの不調・故障(温水式)
不凍液を循環させるポンプが故障すると、温まった不凍液が敷設面まで届かなくなります。ポンプはモーターを使用しているため、経年劣化しやすい部品の一つです。
自分でできる対処法
- 不凍液の残量とエア抜きを確認(温水式)
タンク内の液面をチェック。減っていれば補充を。(密閉式の場合は自身での補充作業ができません。)
エア抜きバルブを少し開けて空気を抜くのも有効ですが、密閉式で圧力が低下してしまうようであれば専門業者による調整作業が必要になります。
- コントローラー設定を再確認
設定温度が低すぎないか、降雪モードになっているか確認しましょう。
とはいえ、実際にロードヒーティングが動かないときに、自分での判断が難しいケースも多いです。改善しない場合は専門業者にご相談下さい。札幌ニップロでも、点検や修理を承ります。
【症状③】変な音がする・異臭がする
ロードヒーティングが稼働中に「ゴー」「ガラガラ」「キュルキュル」といった異音や、焦げたような異臭がする場合は、機器内部の部品に深刻な問題が起きている可能性があります。内部部品の故障やショートの可能性もあるため、使用を中止して点検をご依頼ください。
考えられる原因
- コントローラー内部のショート・過熱
焦げたような匂いがする場合は、コントローラー内部で配線がショートしたり、部品が過熱している可能性が高いです。これは非常に危険な状態なので、直ちに電源を切りましょう。
- 電磁弁や制御盤の不具合
電磁弁の作動音や、制御盤内部の部品が異常な音を発している可能性も考えられます。
自分でできる対処法
- 直ちに電源を切る:異音や異臭がする場合は、何よりもまずロードヒーティングのブレーカーを落として電源を遮断してください。
- 専門業者に連絡:これらの症状は、放置すると火災やさらなる機器の破損につながる危険性があります。絶対に自分で原因を探ろうとせず、すぐに専門業者に使用を中止して点検をご依頼ください。
故障を防ぐ!ロードヒーティングのメンテナンス習慣
故障の原因を理解することは大切ですが、そもそも故障を防ぐための日頃のメンテナンスも重要です。ロードヒーティングを長く安全に使うために、以下の点をチェックしましょう。
- シーズン前の試運転
雪が降る前に一度スイッチを入れ、動作確認を。異音やエラーがないかチェック。不凍液の残量確認もこの時期に行うのが理想的です。
- 温水式の場合、不凍液の定期交換
不凍液はメーカーが推奨する期間(一般的に7~8年年)を目安に交換をしましょう。
- リモコン・センサーの清掃:
雪やゴミ、落ち葉などでセンサーが覆われてしまうと、正確な温度や降雪を検知できず、誤作動や非作動の原因になります。こまめに清掃しましょう。
修理か交換か?判断の目安
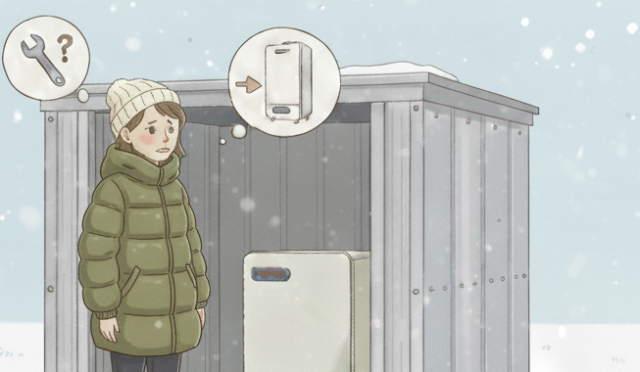
ロードヒーティングの不調が判明した場合、最も知りたいのは「どの部品を直せばいいのか」「修理で済むのか」という点でしょう。ボイラーやセンサーなど、部品ごとの交換が最も費用対効果が高いケースについて解説します。
部品交換で修理を検討
- センサーの故障:センサーは経年劣化しやすい部品ですが、システムの心臓部は生きているため、最も修理しやすいケースです。費用は数万円~。
- サーモスタット、電磁弁の故障:これらの制御系の小さな部品も、交換による修理で対応できます。
- 循環ポンプの故障(温水式):ポンプ単体の交換で対応可能です。ただし、設置から年数が経っている場合は、ボイラー交換と同時に行うか検討が必要です。
ボイラー本体の交換を検討
- 温水ボイラーの寿命(10年〜15年):設置から10年を過ぎると、点火不良などボイラー本体の燃焼系トラブルが増加します。ボイラーの修理を繰り返すより、新品のボイラーに交換する方が、ランニングコストの改善にも繋がり、費用対効果が高いことが多いです。
まとめ:ロードヒーティングの不調は早めの点検が大切
ロードヒーティングの不調は、原因が多岐にわたりますが、多くの場合、早めの点検と適切な対処で解決できます。
「おかしいな」と思ったら、まずは基本のチェック。それでも直らないときは、専門業者に早めの点検を依頼しましょう。
お問い合わせについて
修理のご依頼、ご相談、無料の見積もりはお気軽にお問い合わせください。
🕘 【営業時間】9:00〜17:00/⛔ 日曜・祝日定休
- お電話: 0120-101041
- WEBフォーム
- LINE


